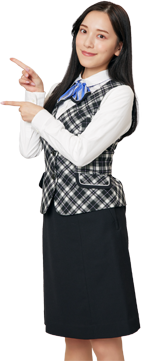自動車コラム
ハイブリッド車、EV車の豆知識

皆さんは、ハイブリッド車とEV車のことをどれくらいご存じでしょうか。どちらの車両も、現在では一般的になっており多くの方が、どういったものかある程度の知識はあるかと思います。今回は、それぞれの車両にまつわる豆知識を紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
目次
ハイブリッド車のバッテリーを長持ちさせるメンテ術
ハイブリッドの車両は電気モーターとガソリンエンジンを組み合わせています。そのため、燃費性能が高められる点や環境性能が高い点などがメリットの車両です。ハイブリッド車では、電気モーターを稼働させ、エネルギーを効率的に再利用します。ハイブリッド車を走らせる場合、電気だけで走らせるモードとガソリンで走らせるモードを選べます。最適なパワーを選択し効率的にエネルギーを使用できるためおすすめです。
【バッテリーを長持ちさせるには次の方法】
・バッテリー(補助バッテリー)やモーターの定期点検
・温度管理をするためにカバーをかける
・過充電にならないように気をつける
・急発進や急加速はせず丁寧な運転を心がける
以上のことに気をつけることで、バッテリーを長持ちさせられます。
特に、走行中の乗り方でバッテリーの寿命を長持ちさせられるので注意が必要です。運転によるバッテリーへの負担が大きくなると劣化する可能性があります。丁寧な運転を心がけたうえで、エコモードなどの活用もご検討ください。
ハイブリッド車でもガソリンは常に満タンがいいの?

クルマのガソリンは、ガス欠を防ぐため満タンに入れることがあるかと思います。震災の件も含め、満タンにすると安心です。しかし、ハイブリッドモデルの場合はガソリンを満タンにすると、ガソリンを劣化させる恐れがあるため注意しましょう。
ハイブリッド車で走行する時にガソリンモードで走る機会が多ければ、ガソリンの給油が必要です。しかし、電気モードで走らせる機会が多い場合にはガソリンが残ってしまい劣化する可能性があります。そのため、ハイブリッド車であっても走らせる状況に応じて給油の状況は検討すべきといえるでしょう。
EVの効率良い充電サイクル:充電設備との相性も解説
電気自動車の効率良い充電サイクルはどういったものがあるのでしょうか。EV車両を充電するときの必要な時間は具体的に以下の3つです。
【EVに関わる時間】
1. 充電場所への移動時間
2. 充電する時間
3. 充電待ちの時間
上記のEV充電に関わる時間を意識してドライブルートを検討することがポイントです。
充電場所は、目的地の間で検討すると尽きる前に充電できます。充電スポットを検索するWebサイトが複数あるので、活用をおすすめします。最近では、ショッピングモールなどの商業施設や市役所などの場所でも充電できるため、ガソリンスタンド以外の充電スポットがあることも覚えておきましょう。
充電時間についても、少しずつ充電をしていく方法や待ち時間を快適に過ごせるような場所がおすすめです。充電スポットの数が多いところや運転手の休憩を兼ねた場所で充電をすると、ロスタイムとならずに済みます。充電に必要な時間は車両によって異なるので、事前に把握しておきましょう。
EV車独特のメンテナンス

EV自動車では、クルマの基本的なメンテナンスだけでなくEVならではのメンテナンスが必要です。具体的に必要なメンテナンスは「バッテリー」のメンテナンスです。バッテリーの劣化が起こると走行距離が短くなってしまうため、定期的な点検や状況によっては交換を検討すると良いでしょう。
一般的に、バッテリーの寿命は8~15年程度といわれています。メーカーや車種、クルマの使用状況によってバッテリーの寿命が異なるので、自分の車両がどれくらいのものか事前に確認しておくと安心です。
そのほか、具体的に以下3点のメンテナンスを紹介します。
・プラグ周りメンテナンス
・夏冬での消費量の違い
・バッテリー上がり時の対応方法
次項より詳しく解説するので、ご参考にしてください。
プラグ周りメンテナンス

EV自動車にはエンジンが搭載されていないため、エンジンを稼働させるためのプラグは基本的に搭載されていません。しかしながら、EV用のプラグが存在しています。
車載の駆動用バッテリーから高電圧の電力を流しているため、バッテリーなどの周辺を定期的に点検する必要があります。その際、一時的に高電圧の電流を止めないと大変危険です。この電気を遮断するために使われるプラグが「サービスプラグ」です。サービスプラグを外すと点検できますが、外してから10分以上時間を置く必要があります。
しかし、電気周辺の点検などは大変危険なので、専門の方などの知識をもっている方が対応してくれるほうが安心です。一般の方はなるべく触らないようにしましょう。
夏冬での消費量の違い
電気の消費量は、季節ごとで異なるイメージがあるかもしれません。この点に関しては、EV自動車を使用している環境によって異なります。東京や関東などの比較的温度差がそこまで大きくないところであれば、大きな差はありません。
しかし、極寒地や氷点下の環境で駐車をするなどの気温差が生じる場合は、消費量が悪化する可能性があります。覚えておきましょう。
バッテリー上がり時の対応方法
EV自動車もバッテリー上がりが起こるのでしょうか。ここでは、普通車と違うバッテリー上がりの対応方法を紹介します。
EV自動車は、駆動用バッテリーと補機用バッテリーの2つが搭載されています。駆動用は文字通り、エンジン搭載車両と同じ役割をもつ自動車を動かすためのバッテリーです。補機用は、アクセサリー(オーディオやエアコンなど)を動かすために使うバッテリーです。補機用のバッテリーは、駆動用バッテリーから電気を補充して必要な電圧が保持できるようになっています。そのため、基本的にはバッテリー上がりは起きにくいといえるでしょう。
しかしながら、駐車中にライト・ルームランプの消し忘れをするとバッテリーが上がってしまいます。補機用バッテリー上がりは、システム起動前にメーター内の警告灯がやや暗くなって標示されるので把握できることでしょう。システムの起動ができず、走行不能となってしまうので注意しなくてはなりません。
また、駆動用バッテリーでも電欠(ガス欠と同じような状態)の場合、バッテリー上がりと同じ状態です。メーターに、バッテリー充電量が下がっていることをドライバーに伝えてくれます。そのうえで、必要最小限のスピードしか出ないので注意してください。
バッテリー上がりは次の方法で解決しましょう。
①駆動用バッテリーの場合:近所で充電できるのであれば問題ありませんが、動けない場合はJAFを呼んで対応してもらいましょう。無理に動かして道路上で停車するほうが危険です。
②補機用バッテリーの場合:ガソリン車と同様にほかの自動車から電気を分けてもらうことで解決できます。しかし、充電で解決できない場合はバッテリーの交換が必要かもしれません。
バッテリー上がりの場合は、JAFなどの専門家を呼んで解決する方法が一番なので覚えておきましょう。
EV車の電池消費が早くなったと感じたら?
EV自動車の電池消費が早くなったと感じる原因は「過充電」もしくは「過放電」をしている可能性が考えられます。電池の容量が100%超えているにも関わらず電圧をかけ続けた状態が過充電、電池容量が0%以下になるまで放電する状態を過放電といいます。バッテリーを劣化させてしまうことで電池消費が早まる可能性があります。つまり、充電の仕方に注意して使用することで劣化を防げるため電池消費を抑えられるかもしません。
EV自動車を活用するためにもどのように充電をするか、どのように使用するかを考えて走らせましょう。
まとめ:ハイブリッドとEV車の違いを理解して購入を検討しよう!
ハイブリッド車とEV自動車は、それぞれ良いところも気をつけなくてはならないところもあります。しかし、それぞれの違いをしっかり把握したうえで生活状況に応じた車両を選ぶと、より豊かな自動車ライフを送れるのでおすすめです。環境への配慮をしながら、快適なドライブを楽しむためにもハイブリッド車もしくはEV自動車を活用しましょう。